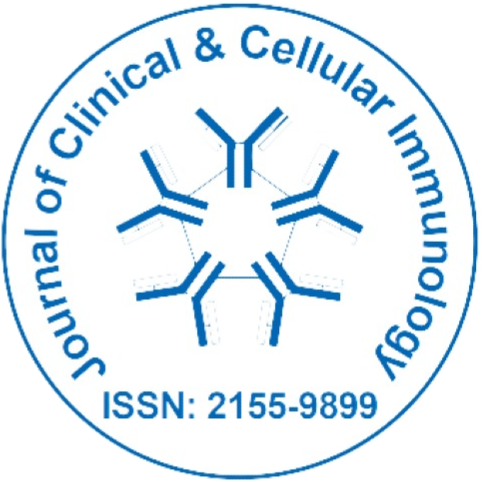
ķ¤│ÕŻ░ÕŁ”Ńü©Ķü┤Ķ”ÜÕŁ”ŃéĖŃāŻŃā╝ŃāŖŃā½
Ńé¬Ńā╝ŃāŚŃā│ŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣
ISSN: 2155-9899
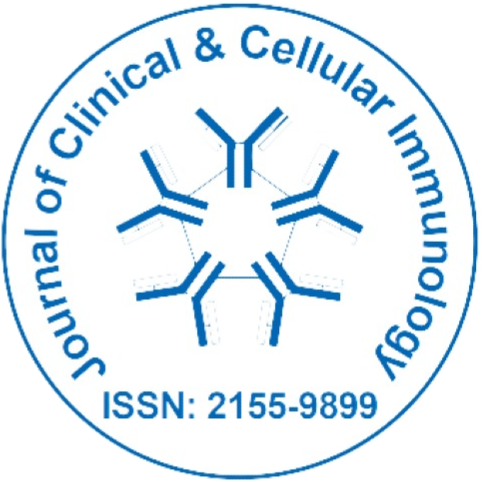
ISSN: 2155-9899
ŃéóŃāŖŃā╗CŃā╗ŃāŁŃā│ŃāēŃā╝ŃāŗŃā¦Ńü©Ńé½Ńā½ŃāŁŃé╣Ńā╗AŃā╗ŃāóŃā®
ĶāīµÖ»:ńÅŠÕ£©ŃĆüÕżÜńÖ║µĆ¦ńĪ¼Õī¢ńŚćŃü«µ▓╗ńÖéŃü½Ńü»ń¢ŠµéŻõ┐«ķŻŠńÖéµ│ĢŃüīÕł®ńö©ÕÅ»ĶāĮŃü¦ŃüéŃéŗŃü½ŃééŃüŗŃüŗŃéÅŃéēŃüÜŃĆüÕåŹńÖ║Õ»øĶ¦ŻÕ×ŗŃüŠŃü¤Ńü»µŚ®µ£¤ķĆ▓ĶĪīÕ×ŗŃü«ń¢ŠµéŻŃü¦ķćŹÕ║”Ńü«ńź×ńĄīµ®¤ĶāĮķÜ£Õ«│Ńü½Ķŗ”ŃüŚŃéƵéŻĶĆģŃüīŃüäŃüŠŃüĀŃü½ÕŁśÕ£©ŃüÖŃéŗŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü«µéŻĶĆģŃü½Ńü©ŃüŻŃü”ŃĆüĶć¬Õ«ČķĆĀĶĪĆÕ╣╣ń┤░Ķā×ń¦╗µżŹŃü»õĖŹÕÅ»ķĆåńÜäŃü¬ķÜ£Õ«│ŃüĖŃü«ķĆ▓ĶĪīŃéÆķś▓ŃüÉķćŹĶ”üŃü¬µ▓╗ńÖéŃéĮŃā¬ŃāźŃā╝ŃéĘŃā¦Ńā│Ńü©Ńü¬ŃéŗŃĆéķüÄÕÄ╗ 20 Õ╣┤ķ¢ōŃü½ÕżÜµĢ░Ńü«ńĀöń®ČŃüīĶĪīŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü½ŃééŃüŗŃüŗŃéÅŃéēŃüÜŃĆüÕżÜńÖ║µĆ¦ńĪ¼Õī¢ńŚćŃü½ŃüŖŃüæŃéŗĶć¬Õ«ČķĆĀĶĪĆÕ╣╣ń┤░Ķā×ń¦╗µżŹŃü«µéŻĶĆģńĄäŃü┐ÕģźŃéīÕ¤║µ║¢ŃĆüµ£½µóóĶĪĆÕ╣╣ń┤░Ķā×ÕŗĢÕōĪŃüŖŃéłŃü│ķ¬©ķ½äń┤░Ķā×Ńé│Ńā│ŃāćŃéŻŃéĘŃā¦ŃāŗŃā│Ńé░Ńü«ŃāŚŃāŁŃāłŃé│Ńā½ŃĆüŃüŖŃéłŃü│Ķ┐ĮĶĘĪĶ¬┐µ¤╗Ńü«µ¢╣µ│ĢŃü»ÕÄ│Õ»åŃü½ńĄ▒õĖĆŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃĆé
µ¢╣µ│Ģ:µéŻĶĆģŃü«ń¢ŠµéŻŃéĄŃā¢Ńé┐ŃéżŃāŚŃĆüń¢ŠµéŻµ£¤ķ¢ōŃü«ń»äÕø▓ŃĆüķÜ£Õ«│ŃĆüµ£½µóóĶĪĆÕ╣╣ń┤░Ķā×ÕŗĢÕōĪŃüŖŃéłŃü│ķ¬©ķ½äń┤░Ķā×Ńé│Ńā│ŃāćŃéŻŃéĘŃā¦ŃāŗŃā│Ńé░Ńü«Ńā¼ŃéĖŃāĪŃā│ŃĆüń¦╗µżŹÕŠīŃü«ńö╗Õāŵż£µ¤╗Ńü«Ńé╣Ńé▒ŃéĖŃāźŃā╝Ńā½ŃĆüŃüŖŃéłŃü│ŃüōŃéīŃéēŃü«ńĀöń®ČŃü½õĖĆĶ▓½ŃüŚŃü”ķü®ńö©ŃüĢŃéīŃü¤Ķć©Õ║Ŗµż£µ¤╗ŃāÉŃéżŃé¬Ńā×Ńā╝Ńé½Ńā╝Ńü«µ¼ĀÕ”éŃéÆÕɽŃéĆńÖ╗ķī▓µ¢╣µ│ĢŃü½Õż¦ŃüŹŃü¬ķüĢŃüäŃüīŃüéŃéŗŃü½ŃééŃüŗŃüŗŃéÅŃéēŃüÜŃĆüń¦╗µżŹŃü«Ķē»ÕźĮŃü¬Ķ╗óÕĖ░ŃéÆńó║Ķ¬ŹŃüŚŃü¤µ£ĆĶ┐æŃü« 5 õ╗ČŃü«Ķć©Õ║ŖńĀöń®ČŃéÆŃā¼ŃāōŃāźŃā╝ŃüŚŃü¤ŃĆé
ńĄÉµ×£:Ķć¬Õ«ČķĆĀĶĪĆÕ╣╣ń┤░Ķā×ń¦╗µżŹŃü½ŃéłŃéŗµ▓╗ńÖéŃü»ŃĆüń¢ŠµéŻõ┐«ķŻŠńÖéµ│ĢŃéÆÕÅŚŃüæŃü¤µéŻĶĆģŃü©µ»öĶ╝āŃüŚŃü”ŃĆüń¦╗µżŹÕŠīŃü½ń¢ŠµéŻµ┤╗ÕŗĢńŖȵģŗŃü«Ķ©╝µŗĀŃüīŃü¬ŃüäńŖȵģŗŃéÆńČŁµīüŃü¦ŃüŹŃéŗµéŻĶĆģŃü«Õē▓ÕÉłŃüīµ£ēµäÅŃü½ķ½śŃüäŃüōŃü©ŃüŗŃéēŃĆüķćŹÕ║”Ńü«ÕåŹńÖ║Õ»øĶ¦ŻÕ×ŗŃüŠŃü¤Ńü»µŚ®µ£¤ķĆ▓ĶĪīÕ×ŗń¢ŠµéŻŃü«ĶŗźÕ╣┤µéŻĶĆģŃü½µ£ĆĶē»Ńü«ńĄÉµ×£ŃéÆńż║ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃā¼ŃāōŃāźŃā╝ŃüŚŃü¤ńĀöń®ČŃü¦Ńü»ŃĆüķćŹĶ”üŃü¬µ©¬µ¢ŁńÜäÕĘ«ńĢ░ŃüīĶ”ŗŃüżŃüŗŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ńĄÉĶ½¢:ÕżÜńÖ║µĆ¦ńĪ¼Õī¢ńŚćŃéÆÕ╝ĢŃüŹĶĄĘŃüōŃüÖŃüōŃü©Ńüīń¤źŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗńÅŠÕ£©Ńü«ńö¤ńÉåńŚģńÉåÕŁ”ńÜäŃāĪŃé½ŃāŗŃé║ŃāĀŃü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü¤ŃāÉŃéżŃé¬Ńā×Ńā╝Ńé½Ńā╝Ńü«ÕģĘõĮōńÜäŃüŗŃüżµģÄķćŹŃü¬ķüĖµŖ×Ńü»ŃĆüĶć¬Õ«ČķĆĀĶĪĆÕ╣╣ń┤░Ķā×ń¦╗µżŹŃüŖŃéłŃü│ŃāĢŃé®ŃāŁŃā╝ŃéóŃāāŃāŚ ŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣Ńü«Ńü¤ŃéüŃü«ŃéłŃéŖķü®ÕłćŃü¦µŚ®µ£¤Ńü«µéŻĶĆģķüĖµŖ×Ńü½Ķ▓óńī«ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéµ▓╗ńÖéķ¢ŗÕ¦ŗµÖéŃüŖŃéłŃü│ÕģŹń¢½Õ┐£ńŁöŃü«ÕåŹµ¦ŗń»ēŃü«ŃāĢŃé®ŃāŁŃā╝ŃéóŃāāŃāŚÕŠīŃü«ŃāÉŃéżŃé¬Ńā×Ńā╝Ńé½Ńā╝Ńü«µĖ¼Õ«ÜŃü½ŃéłŃéŖŃĆüÕ«óĶ”│ńÜäŃü¦µĖ¼Õ«ÜÕÅ»ĶāĮŃü¬ÕÅŹÕ┐£ŃüīÕŠŚŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ŃéłŃüåŃü¬ŃāæŃā®ŃāĪŃā╝Ńé┐Ńā╝Ńü«ķü®ńö©Ńü»ŃĆüń¢ŠµéŻŃü«ńŚģÕøĀŃü«ńÉåĶ¦ŻŃéƵĘ▒ŃéüŃéŗŃü«Ńü½ŃééÕĮ╣ń½ŗŃüĪŃüŠŃüÖŃĆé