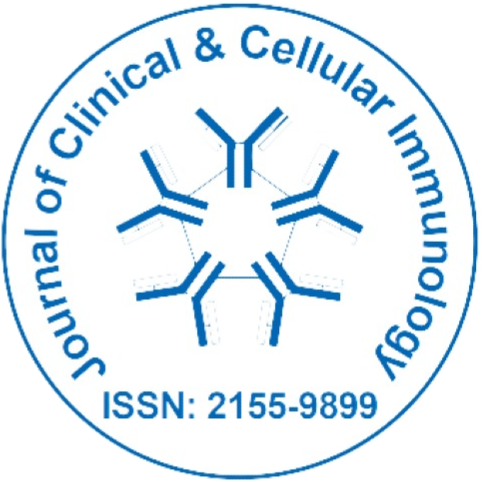
音声学と聴覚学ジャーナル
オープンアクセス
ISSN: 2155-9899
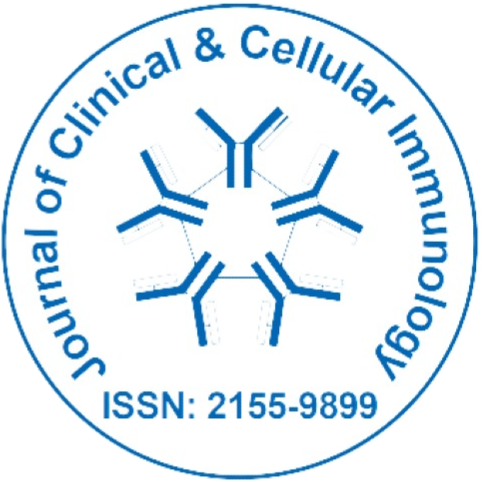
ISSN: 2155-9899
„É¥„Ç£„ɺ„DZ„ɪ„Éï„É≠„ǧ„Éá„É≥„Éñ„É´„ÇØ„ÄÅ„Éû„ÉÄ„Éï„ɪ„Ç¥„ɺ„Çø„ÉÝ„ÄÅ„Éó„É©„Éá„Ç£„Éó„Çø„ɪ„ÉÅ„É£„ÇØ„É©„Éú„É´„ÉÜ„Ç£„ÄÅ„Ç∏„É£„ɨ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Ç∏„Ç߄ɺ„ÉÝ„Çπ„ÄÅ„Ç∏„Çß„Éã„Éï„Ç°„ɺ„ɪ„É™„ÉÅ„É£„ɺ„Ç∫„ÄÅ„Ç¢„É™„ÇΩ„É≥„ɪS„ɪ„ǵ„É´„É¥„Ç°„Éà„ɺ„É™„ÄÅ„Ç¢„ɺ„É≠„É≥„ɪ„Éú„ɺ„É´„Éâ„Ƕ„Ç£„É≥„ÄÅ„Ç∏„É´„ɪ„Ç∑„É•„É™„Ç®„É؄ɺ„ÄÅR„ɪ„Éû„ɺ„Ç؄ɪL„ɪ„Éñ„É©„ɺ„ÄÅ„Ç∏„Éß„É≥„ɪA„ɪ„Ç≥„ɺ„Éô„ÉÉ„Éà„ÄÅ„Éâ„É≠„Çø„ɪ„Çπ„Ç≥„Ƕ„Ç£„É©
1 ÂûãÁ≥ñÂ∞øÁóÖ„ÅØ„Äńǧ„É≥„Çπ„É™„É≥„ÇíÁî£Áîü„Åô„ÇãËܵËáì β Á¥∞ËÉû„ÅÆËá™Â∑±ÂÖçÁñ´Áݥ£ä„Å´„Çà„Å£„Ŷ˵∑„Åì„Çä„Åæ„Åô„ÄÇÂÖçÁñ´„Éó„É≠„ÉÜ„Ç¢„ÇΩ„Éº„ÉÝ„ÅØ„ÄÅ11S/PA28 Ê¥ªÊÄßÂåñÂõÝÂ≠ê„Å®ÂÖ±Âêå„Åó„Ŷ MHC „ÇØ„É©„Çπ I ÂàÜÂ≠ê„Å´„Çà„Å£„ŶÊèêÁ§∫„Åï„Çå„ÇãÂÖçÁñ´ÂéüÊÄß„Éö„Éó„ÉÅ„Éâ„ÇíÁîüÊàê„Åô„Çã„Éó„É≠„ÉÜ„Ç¢„ÇΩ„Éº„ÉÝ„ÅƉ∏ÄÁ®Æ„Åß„ÄÅ„Åì„ÅÆÁóÖÊ∞ó„ÅÆÁô∫Áóá„Å´Èñ¢‰øÇ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åì„Å®„ÅØÈï∑„ÅÑÈñìÊåáÊëò„Åï„Çå„Ŷ„Åç„Åæ„Åó„Åü„Åå„ÄÅËܵËáì β Á¥∞ËÉû„Å´„Åä„Åë„ÇãÂÖçÁñ´„Éó„É≠„ÉÜ„Ç¢„ÇΩ„Éº„ÉÝ„ÅÆÊ©üËÉΩ„Å®Ë™øÁØÄ„Å´„ŧ„ÅфŶ„Å؄Ū„Å®„Çì„Å©„Çè„Åã„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇ„Åì„Çå„Çâ„ÅÆÂïèÈ°å„Å´ÂØæ„Åô„ÇãËààÂë≥Ê∑±„ÅÑÊ¥ûÂØü„ÅØ„ÄÅ„Éí„Éà„Åä„Çà„Å≥ÂãïÁâ©„É¢„Éá„É´„Å´„Åä„Åë„ÇãÁ≥ñÂ∞øÁóÖÁä∂ÊÖã„ÅÆË™òÁô∫„Å´Èñ¢‰øÇ„Åô„Çã I Âûã IFN „Åß„ÅÇ„Çã„ǧ„É≥„Çø„ɺ„Éï„Çß„É≠„É≥ β (IFNβ) „Ç퉪ã„Åó„ÅüÂàùÊúü„ÅÆÊäó„Ƕ„ǧ„É´„ÇπÈò≤Âæ°‰∏≠„Å´ËܵËáì β Á¥∞ËÉû„ÅßÁô∫Áèæ„Åô„ÇãÂÖçÁñ´„Éó„É≠„ÉÜ„Ç¢„ÇΩ„Éº„ÉÝ„ÅÆÊúÄËøë„ÅÆÂàÜÊûê„Åã„ÇâÂæó„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇFreudenburg „Çâ„ÅØ„ÄÅ„Éû„Ƕ„Çπ„ÅÆËܵÂ≥∂„Å® MIN6 „ǧ„É≥„Çπ„É™„Éé„ɺ„ÉûÁ¥∞ËÉûÊÝ™„Çí‰ΩøÁÅó„Ŷ„ÄÅ IFNβ„ÅØ„ÄÅÂè§ÂÖ∏ÁöÑ„Å™ÂÖçÁñ´Ë™òÂ∞éÂõÝÂ≠êIFNγ„Å®Âü∫Êú¨ÁöÑ„Å´ÂêåÊßò„ÅÆÊñπÊ≥ï„ÅßÂÖçÁñ´„Éó„É≠„ÉÜ„Ç¢„ÇΩ„Éº„ÉÝ„Åä„Çà„Å≥11S/PA28Ê¥ªÊÄßÂåñÂõÝÂ≠ê„ÅÆÁô∫Áèæ„ÇíÂà∫ÊøÄ„Åó„ÄÅmRNA„ÅÆËìÑÁ©ç„Å®Ê∏õÂ∞ë„ÅÆ„Çø„ǧ„Éü„É≥„Ç∞„Å剺º„Ŷ„Åä„Çä„Äʼn∏ª„Å´IRF1„Å´„Çà„Å£„Ŷ™퉪ã„Åï„Çå„ÇãÂêåÊßò„ÅÆ˪¢ÂÜôÊ¥ªÊÄßÂåñ„Å®„ÄÅÂêåÊßò„ÅÆmRNA„Åä„Çà„Å≥„Çø„É≥„Éë„ÇØË≥™„ɨ„Éô„É´„ÇíÊåńŧ„Åì„Å®„Åå„Çè„Åã„Å£„Åü„ÄÇ„Åï„Çâ„Å´„ÄÅIFNβ„ÇÇIFNγ„ÇÇ„ÄÅÈÄöÂ∏∏„ÅÆ„Çø„É≥„Éë„ÇØË≥™ÂàÜËߣ„ǵ„Éñ„ɶ„Éã„ÉÉ„Éà„ÅÆÁô∫Áèæ„Çí§âÂåñ„Åï„Åõ„Åö„ÄÅ„Çø„É≥„Éë„ÇØË≥™ÂàÜËߣ„Ç≥„Ç¢„Å∏„ÅÆÁµÑ„ÅøË溄Åø„Çí¶®„Åí„Å™„Åã„Å£„Åü„ÄÇ„Åù„ÅÆÁµêÊûú„ÄÅÂÖçÁñ´„Éó„É≠„ÉÜ„Ç¢„ÇΩ„Éº„ÉÝ„ÅØÂÖçÁñ´ÈÉ®‰Ωç„Å®ÈÄöÂ∏∏„ÅÆ„Çø„É≥„Éë„ÇØË≥™ÂàÜËߣÈÉ®‰Ωç„ÅÆÁ¢∫ÁéáÁöÑÁµÑ„ÅøÂêà„Çè„Åõ„ÇíÊåÅ„Å°„ÄÅ„Åì„ÅÆÈÖçÁΩÆ„Å´„Çà„Çä„ÄÅÂõ∫Êúâ„ÅÆÂÖçÁñ´ÂéüÊÄß„Éö„Éó„ÉÅ„Éâ„ÅåÁîüÊàê„Åï„Çå„ÇãÁ¢∫Áéá„ÅåÈ´ò„Åè„Å™„Çã„Å®ËÄÉ„Åà„Çâ„Çå„Çã„ÄÇ„Åó„Åã„Åó„ÄÅÂÖçÁñ´„Éó„É≠„ÉÜ„Ç¢„ÇΩ„Éº„ÉÝ„ÅØ„ÄÅATPÊûØÊ∏á„ÅÆÊù°‰ª∂‰∏ã„Åß„ÅÆ„Åø11S/PA28„Å´„Çà„Å£„ŶʥªÊÄßÂåñ„Åï„Çå„Åü„ÄÇÈ´òATP„ɨ„Éô„É´„ÅßÂÖçÁñ´„Éó„É≠„ÉÜ„Ç¢„ÇΩ„Éº„ÉÝ„ÅÆÊ¥ªÊÄßÂåñ„ÇíÈò≤„Åê„É°„Ç´„Éã„Ç∫„ÉÝ„ÅØ„Åì„Çå„Åæ„ÅßÂݱÂëä„Åï„Çå„Ŷ„Åä„Çâ„Åö„ÄÅÁ¥∞ËÉû„ÅåÂÖçÁñ´„Éó„É≠„ÉÜ„Ç¢„ÇΩ„Éº„ÉÝ„Å®11S/PA28„ÇíËìÑÁ©ç„Åô„ÇãÈöõ„ÅÆÂÖçÁñ´ÂéüÊÄß„Éö„Éó„ÉÅ„Éâ„ÅÆÁîüÊàê„ÇíÊäëÂà∂„Åó„ÄÅATP„ɨ„Éô„É´„Åå‰Ωé‰∏ã„Åó„ÅüÂÝ¥Âêà„Å´„ÅÆ„ÅøÊäóÂéüÂá¶ÁêÜ„ÇíÊ¥ªÊÄßÂåñ„Åß„Åç„Çã„Åü„ÇÅ„Äŧ߄Åç„Å™Âà∂Âæ°ÁöÑÊÑèÁæ©„ÇíÊåńŧÂèØËÉΩÊÄß„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„Çå„Çâ„ÅÆÊñ∞„Åó„ÅÑÁô∫˶ã„Åå„ÄÅÊó©Êúü„ÅÆÊäó„Ƕ„ǧ„É´„ÇπÂèçÂøú„Å®1ÂûãÁ≥ñÂ∞øÁóÖ„ÅÆÁô∫Áóá„Å®„ÅÆÈñ¢ÈÄ£„Å´Âèä„ź„ÅôÂΩ±Èüø„Å´„ŧ„ÅфŶË≠∞Ë´ñ„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ