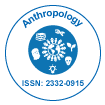
ń║║Úí×ňşŽ
Ńé¬Ńâ╝ŃâŚŃâ│ŃéóŃé»Ńé╗Ńé╣
ISSN: 2332-0915
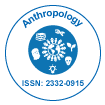
ISSN: 2332-0915
ŃéĄŃâ╗ŃéŞŃâąŃâ│ŃéŽŃéęŃâ│
ŃÇîÚĄŐŠ«ľÚşÜŃÇŹŃüĘŃÇîÚçÄšöčÚşÜŃÇŹŃüĘŃüäŃüćšöĘŔ¬×Ńü»ŃÇüŔ┐Ĺň╣┤ŃÇüšĄżń╝ÜšÁłšŐŠ│üŃü«ňĆŹŠśáŃüĘŃüŚŃüŽšÖ╗ňá┤ŃüŚŃüčŃüîŃÇüŃâÖŃâłŃâŐŃâáŃüžŃü»ŃÇüŃüôŃéîŃéëŃéĺšáöšęÂŃüŚŃüčŔźľŠľçŃü»ŃüöŃüĆŃéĆŃüÜŃüőŃüžŃüéŃéőŃÇ銝ȚĘ┐Ńü»ŃÇüŃâÖŃâłŃâŐŃâáŔż▓ŠŁĹÚâĘŃüźŃüŐŃüĹŃéőÚĄŐŠ«ľÚşÜŃüĘÚçÄšöčÚşÜŃü«ňî║ňłąŃüźŔíĘŃéîŃéőń║║ÚľôŃüĘŔ笚äÂŃü«Úľóń┐éŃüźŃüĄŃüäŃüŽŠĄťŔĘÄŃüÖŃéőŃÇéŔ笚äÂŃü»ŃÇüšĄżń╝ÜšÜäŃü¬ňá┤ŃüĘŃü«Úľóń┐éŃüźň┐ťŃüśŃüŽŃÇüšĄżń╝ÜšÜäŃüźŠžőš»ëŃüĽŃéîŃÇüšĽ░Ńü¬ŃéőŠľ╣Š│ĽŃüžŔÇâŃüłŃéëŃéîŃüŽŃüŹŃüčŃÇéÚçÄšöčÚşÜŃüžŃü»ŃÇüňĹ│ŔŽÜŃüîŔęĽńżíňč║Š║ľŃüžŃüéŃéŐŃÇüŠ▒ÜŠčôŃüĽŃéîŃüŽŃüäŃü¬ŃüäšŐŠůőŃéäń║║ńŻôŃüźŠťëšŤŐŃü¬ŠłÉňłćŃüîÚçŹŔŽľŃüĽŃéîŃéőŃÇéń║║ÚľôŃü«ń╗őňůąŃüźÚľóń┐éŃüŚŃü¬ŃüäŔ笚äÂŃü»Ŕë»ŃüäŃééŃü«ŃüĘŔ¬ŹŔşśŃüĽŃéîŃéőŃÇéń║║ÚľôŃüîŔ笚äÂŃüźń╗őňůąŃüÖŃéőŃüĘŃÇüŔ笚äÂŃü»Š▒ÜŠčôŃüĽŃéîŃÇüń║║ÚľôŃüźŃüĘŃüúŃüŽňŻ╣ŃüźšźőŃüčŃü¬ŃüĆŃü¬ŃéőŃÇéŔ笚äÂŃü»šőČšźőŃüŚŃüčšöčšöúŠÇžŃéĺŠîüŃüíŃÇüšĽĆŠĽČŃü«ň»żŔ▒íŃüžŃüéŃéŐŃÇüŔç¬ňĚ▒ň«îšÁÉšÜäŃüžŃüéŃéŐŃÇüŔç¬ňżőšÜäŃü¬ňşśňťĘŃüžŃüéŃéőŃüĘŃüäŃüćŔŽőŠľ╣Ńü»ŃÇüÚçÄšöčÚşÜŃü«ŠÂłŔ▓╗ŃüźŔíĘŃéîŃüŽŃüäŃéőŃÇéŃüŚŃüőŃüŚŃÇüňĚąŠąşšÜäŃü¬ÚĄŐŠ«ľŃüžŃü»ŃÇüŔ╝Şňç║ŃÇüšöčšöúŠÇžŃÇüšÁłšÜäňłęšŤŐŃü¬ŃüęŃü«ŔŽüš┤áŃüîÚŁ×ňŞŞŃüźÚçŹŔŽľŃüĽŃéîŃÇüÚşÜŃü«Ŕ퍚öčŃüĘŠáäÚĄŐŃüîÚçŹŔŽľŃüĽŃéîŃéőŃÇéÚçÄšöčŃü«Ŕ笚äÂŃü»ńŞŹŔ퍚öčŃüžŃÇüŠ▒ÜŃüĆŃÇüÚçÄŠÇžšÜäŃüžŃÇüňŹ▒ÚÖ║ŃüžŃüéŃéőŃüĘŔÇâŃüłŃéëŃéîŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéń║║ÚľôŃüźŃéłŃéőš«íšÉćŃüźŃéłŃüúŃüŽŃÇüŔ笚äÂŃü«ÚçÄšöčšŐŠůőŃü»ŠťÇň░ĆÚÖÉŃüźŠŐĹŃüłŃéëŃéîŃÇüŔ笚äÂŃü»Ŕ퍚öčšÜäŃüžŃÇüŠ┤╗ňŐŤŃüîŃüéŃéŐŃÇüń║║ÚľôŃüźŃüĘŃüúŃüŽŠťëšöĘŃü¬ŃééŃü«ŃüźŃü¬ŃéŐŃüżŃüÖŃÇéšžĹňşŽšÜäš«íšÉćŃü«ňÉŹŃü«ńŞőŃüźŃÇüňĚąŠąşšÜäŃü¬ÚĄŐŠ«ľŃüžŃü»ŃÇüń║║ÚľôŃü»Ŕ笚äÂŃü«ňŹ▒ÚÖ║ŠÇžŃé嚍┤ŠÄąňĆľŃéŐÚÖĄŃüŹŃüżŃüÖŃÇéńŞÇŠľ╣ŃÇüÚçÄšöčŃü«ÚşÜŃü«ŠÂłŔ▓╗ŃüĘňĚąŠąşšÜäŃü¬ÚĄŐŠ«ľŃüźŃüŐŃüĹŃéőŔ笚äÂŃü»ŃÇüń║║ÚľôŃü«š▓żšą×Ńü«šöúšëęŃüžŃüéŃéŐŃÇüňůĚńŻôšÜäŃü¬ň▒׊ǞŃéĺňÉźŃüżŃü¬ŃüäŠŐŻŔ▒íšÜäŃü¬ŠŽéň┐ÁŃüžŃüÖŃÇéÚçÄšöčŃü«ÚşÜŃü»ŃÇüÚĄŐŠ«ľÚşÜŃüĘŃüŁŃéîŔç¬ńŻôŃüîň»żšźőŃüÖŃéőŃééŃü«ŃüžŃü»ŃüéŃéŐŃüżŃüŤŃéôŃÇéŃüŁŃéîŃü»šĄżń╝ÜšÜäŃüźŠžőš»ëŃüĽŃéîŃÇüŔ笚äÂŔŽ│ŃéĺňĆŹŠśáŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇé